当院における心房細動治療と脳梗塞予防について
医療関係者様へ
病院
医療関係者の皆様へ
その心房細動、抗凝固療法だけで本当に大丈夫ですか?
心房細動は動悸や息切れなどの症状だけでなく、脳梗塞をはじめとする重篤な塞栓症のリスクを高める疾患です。心房細動と診断された患者さんが最初に考えなければならないのは、塞栓症を予防するための抗凝固療法の導入です。それと同時に、心房細動そのものを制御する治療も検討します。一方で、抗凝固療法の導入そのものが難しい患者さんも少なからずおられるため、その対応も考えなければなりません。当院では患者様の状態に応じて、以下の先進的な治療法を提供しています:- カテーテルアブレーション
- WATCHMAN(ウォッチマン)を用いた経皮的左心耳閉鎖術
- 完全内視鏡下外科的左心耳切除術
治療の詳細
カテーテルアブレーション
カテーテルアブレーションは、不整脈の原因となる部位を電気的に焼灼(しょうしゃく)することで正常なリズムを取り戻す治療法です。心房細動を制御する治療効果は薬よりもはるかに強力なものとなります。カテーテルアブレーションによって心房細動を制御することは脳梗塞リスクを減らすことにもつながりますが、この治療単独で脳梗塞を完全に予防できるわけではありません 。当院では循環器内科不整脈担当部長の大塚崇之医師をはじめとする不整脈班が担当いたします。WATCHMANを用いた経皮的左心耳閉鎖術
WATCHMANとは、先端に閉鎖デバイスを装着したカテーテルを用い、左心耳の入口を閉鎖するデバイスです。デバイスは静脈から挿入され、左心房に留置されます。当院では循環器内科担当部長の嘉納寛人医師と不整脈班で連携して行います。主な対象となる患者様:
- 抗凝固薬の長期服用が困難と考えられる方
- 消化管出血など、重篤な出血歴がある方術
- 完全内視鏡下外科的左心耳切除術
完全内視鏡下外科的左心耳切除術
外科的左心耳切除は、胸部に数か所の小さなポートを設けて胸腔鏡を用い、左心耳を切除する低侵襲手術です。人工心肺を使用せず、手術時間は約30分と短時間で行えます。当院では心臓血管外科部長の在國寺健太医師と、心臓血管外科医長の宮本陽介医師が担当いたします。特に以下の患者様に有効です:
- 脳梗塞を既往歴に持つ方
- 抗凝固薬服用中にもかかわらず脳梗塞や脳出血を発症した方
- 重篤な出血リスクがある、または過去に出血歴がある方
- 薬の種類を減らしたい、もしくは服薬を希望しない方
医療機関様へのご案内
心房細動患者様の左心耳マネジメントは、現代医療において非常に重要な課題です。当院は、カテーテルアブレーション、WATCHMAN(ウォッチマン)を用いた経皮的左心耳閉鎖術、完全内視鏡下外科的左心耳切除術のすべてを実施できる、全国的にも限られた医療施設です。
安全で効果的な脳塞栓症予防と心房細動管理を目指し、各治療分野のエキスパートがチームとして連携して患者様一人ひとりの状況に応じて最適な治療法を選択・提供いたします。
不整脈や左心耳に関する治療でご相談がある場合は、以下までお気軽にご連絡ください。
担当医師からのメッセージ
(不整脈担当部長 大塚崇之医師)
心房細動に対するカテーテルアブレーションが開始されてから20年以上が経過し、日本のガイドラインでも自覚症状を有する薬剤抵抗性心房細動に対する適応がClass Ⅰとして推奨されるようになり、近年では高齢者や心不全合併例まで適応が拡大しました。当院でも2006 年より心房細動に対するカテーテルアブレーションを開始し現在まで約4,000 例を施行しております。心房細動に対するカテーテルアブレーションは個々の患者さんに応じて適応を決定しておりますので、適応に悩むような患者さんでも外来で相談しながら治療方針を検討しますので安心してご相談ください。
(循環器内科担当部長 嘉納寛人医師)
当科ではカテーテルを用いた左心耳閉鎖術を行っております。3泊程度の入院で術後もスムーズに生活に戻っていただける低侵襲な治療です。出血でお困りの方、高いリスクがある中で抗凝固薬を続けている方は是非ご相談ください。
(心臓血管外科部長 在國寺健太医師、心臓血管外科医長 宮本陽介医師)
当科では、体への負担が少ない完全内視鏡下の左心耳切除を実施しています。この治療は、抗凝固薬が難しい方や再発リスクでお困りの方にとって非常に有効であり、多くの患者様に知っていただきたい手術です。
心房細動や左心耳のマネジメントは、近年ますます注目されている分野ですが、心房細動の適切な評価から、アブレーション、WATCHMAN、外科的左心耳切除といった治療選択まで考えるのは決して容易ではありません。
私たちは、「心房細動をトータルに相談できる病院」、さらに言えば「心房細動なら心研に任せておけば安心」と思っていただけるよう、患者様お一人お一人の状況に合わせた最適な治療を各分野のエキスパートが協力してご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
(心臓血管研究所研究本部長 鈴木信也医師)
心房細動と診断された患者さんの患者背景は実に多様なものであり、若年の方からご高齢の方まで、併存症のない方から多数の併存症を持つ方まで、さまざまな方がおられます。心房細動の治療はかなりの面で整備されてきたと言えますが、画一的に治療方針が決められるものでもなく、患者さんごとの背景や希望に沿って治療を選択していくという側面があります。そのため、「心房細動と診断されたけれども、どのような治療方針が自分に合っているのか悩ましく思っている」という患者さんが、数多く当院を訪ねて来られます。
当院は心房細動の先進治療のエキスパートがそろっている一方で、心房細動薬物治療のガイドライン委員を務めた経験をもつメンバーがそろっている点も全国有数と言えると思っております。皆が力を合わせて、患者さんに満足のいただける心房細動治療を提供することを目指します。
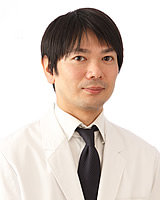 |
 |
 |
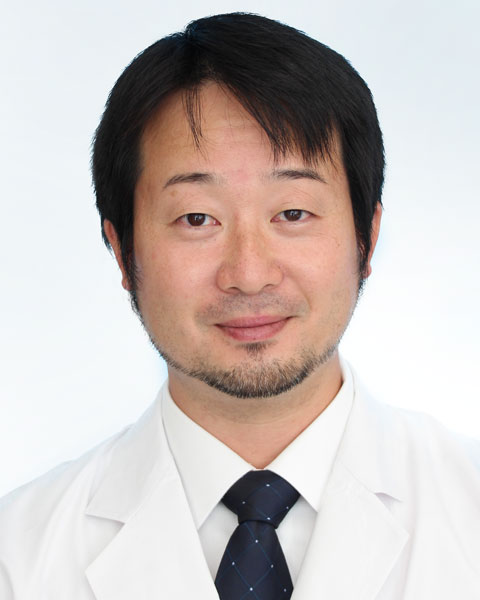 |
 |
| 循環器内科 | 循環器内科 | 心臓血管外科 | 心臓血管外科 | 心臓血管研究所 |
| 不整脈担当部長 | 担当部長 | 部長 | 医長 | 研究本部長 |
| 大塚 崇之 | 嘉納 寛人 | 在國寺 健太 | 宮本 陽介 | 鈴木 信也 |
受診予約
月~金 9:00~17:00 (祝・年末年始除く)
お問い合わせ
急患の方は24時間随時診察いたします
サイト内リンク一覧


